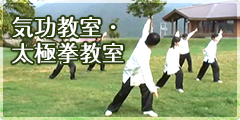大腿骨骨折損傷と骨粗鬆症について
私のところには、なぜか同じような症状の方が続けて訪れることがある。
以前にも、国内に約一万人とされるALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者さんが、同じ時期に二人通われていたことに驚いたことがある。今回の話題はそのALSではないが、これと似た不思議な“重なり”が起きた。
私には何人か弟子がいるが、皆、心根のやさしい人たちだ。そのうち二人の弟子のお母さんが、なんと1週間と空けずに「大腿骨骨折」で入院することになった。お母さん思いの弟子から相談を受けたので、「入院して治すのがいちばん」と即答した。
なんでもかんでもMMSで治るわけではない。
■ 大腿骨骨折とは何か
大腿は、重い上半身を支えるため常に大きな負担がかかっている。もし大腿骨が骨粗鬆症によって密度の低いスカスカの状態になっていれば、転倒などのわずかな衝撃でも骨折してしまう。これが大腿骨骨折である。
前兆としては、脚に力が入りづらくなったり、よろけやすくなったりする。
「よろけ=脳の問題」と考える人もいるが、私は筋肉が原因だと捉えている。MMS理論では、固まって使えなくなった筋肉は、常に使用中と同じ状態だ。歩行時に片脚で体を支える瞬間、その筋肉が働かなければ身体は安定せず、よろけが起きる。
■ なぜ骨粗鬆症が起きるのか
骨粗鬆症は高齢者に多いため「加齢のせい」と片付けられることが多い。
一般的な説明では「骨をつくる細胞より、骨を壊す細胞の働きが上回り、さらにカルシウム不足が重なることで骨が弱くなる」とされている。しかし、日ごろカルシウムを摂るようにしているが良くなったという話はあまり聞かない。
- MMSの捉え方
MMSでは、骨も他の組織と同じく代謝を繰り返している点に注目する。
骨には「栄養孔」という穴があり、そこから血液が流れ込む。この血液が十分に流れなくなると、新しい骨をつくる細胞(発芽細胞)が働けず、外側で働く破壊細胞だけが仕事を続けてしまう。
その結果、骨はスカスカになる。
ここで、カルシウムを摂れば骨が良くなる、という考え方がある。だが、血液が届かない場所に栄養だけが届くことはない。血流のないところにカルシウムだけが入っていけるとは考えにくい。
■ なぜ骨の血流が悪くなるのか
考えられる要因は二つある。
・骨内部の血管が、周囲の硬くなった筋肉に押しつぶされる
・骨を覆う筋膜の上にある筋肉が硬くなり、血流を阻害する
多くの場合、この二つが同時に起きている。
■ 改善には時間が必要
骨粗鬆症が起きている部位の筋肉をほぐし、血流を回復させれば、骨の再生は進んでいく。ただし、血流を再開してもすぐに骨が戻るわけではない。2〜3か月の時間が必要になる。
「歩いて足を鍛えればよい」と言う人もいる。しかしこの方法を私は勧めない。もっと深刻になる場合が多い。
確かに運動は大事だ。しかし中には、膝の痛みや坐骨神経痛などで動きたくても動けない人もいる。そのような人に「運動しろ」と言っても無理がある。整形外科や骨継ぎの施術者に速やかに治せる技術があれば容易なことなのだが?
■ おわりに
今回、弟子のお母さんの骨折が続けて起きたことをきっかけに、大腿骨骨折と骨粗鬆症について、MMSの視点から考えてみた。
身体は「骨・筋肉・水」で成り立っている。代謝も血流も、筋肉の柔らかさも、すべてがつながってひとつの身体を形づくっている。
骨の健康についても、この全体の流れの中で理解していくことが大切だと思う。
眞々田昭司|2025/11/20